税理士 高橋龍二
1957年、山形県尾花沢市生まれ。1982年、税理士試験合格。1987年、税理士登録。2022年、税理士法人伊藤・高橋事務所を開設し、代表社員税理士となる。日本税理士会連合会理事、東北税理士会副会長、東北税理士会山形県支部連合会会長(いずれも2023年7月退任)。多くのクライアントとともに、地方において豊かに暮らしていくことを目指している。
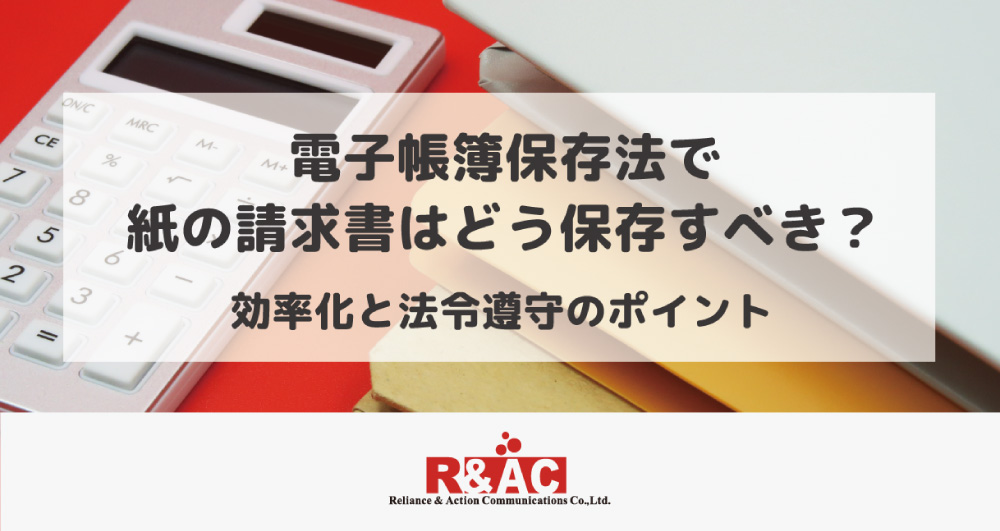
2024年の電子帳簿保存法改正により、紙の請求書の扱いに頭を悩ませる担当者は多いでしょう。電子帳簿保存法への対応では「法令遵守」と「効率化」のバランスが大切です。
紙の請求書も電子データの請求書も、それぞれ定められた方法で適切に保存しつつ、ITを活用して効率的に管理することが求められます。
本記事を読めば、紙で受け取った請求書の適切な保存方法について、業務効率化と法令遵守の両面からポイントがわかります。
目次
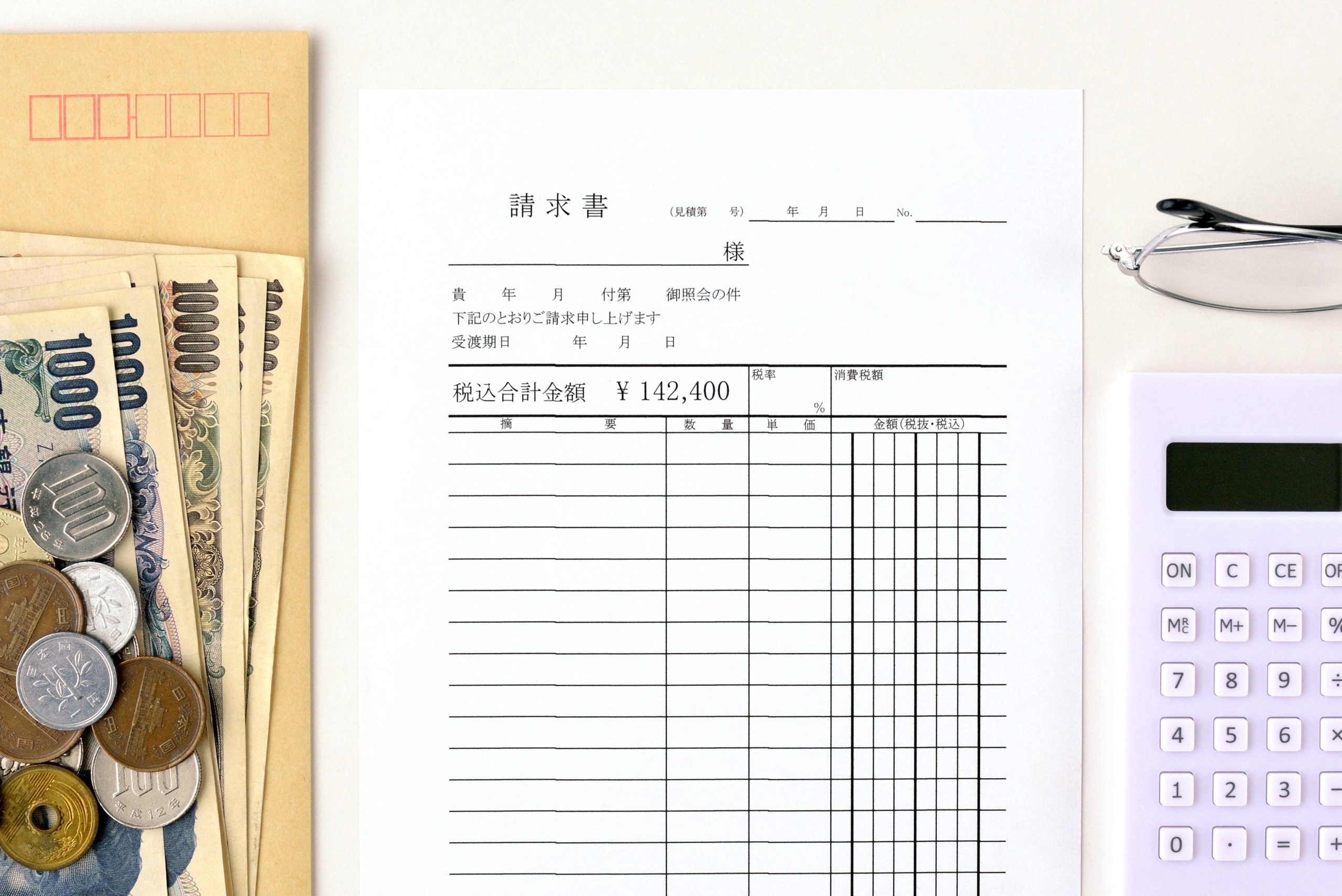
結論としては、紙で受領した請求書は紙のまま保存できます(必要に応じて電子化も可能)。一方、電子データで受領した請求書は紙に印刷して保存することは認められておらず、電子データのまま保存する必要があります。
電子帳簿保存法とは、「国税関係書類を電子データで保存するための法律」です。書類上の手続きというものは年月を経るごとにどうしても複雑化してしまう面がありますから、このようなデジタル化によって業務効率化・コスト削減・税務手続きの簡素化をしよう、という意義があります。この法律により、帳簿や請求書などをデータで保管する際のルールが定められています。
ルールとしては、紙の請求書(郵送や手渡しでもらったもの)は紙の原本のまま保管して問題ありませんし、一定の要件を満たせばスキャナで電子データ化して保存することも認められています。
一方、Eメールやウェブで受領した電子請求書(PDF等のデータ)は電子取引に該当し、データの形で保存することが義務となります。紙に印刷してファイリングするだけでは法律上の保存とは認められません。電子取引で受け取った請求書は、必ず元の電子データのまま保管する必要があります。
つまり、
というのが基本ルールです。それぞれの具体的な方法とポイントは以下の通りです。
※参考:電子取引データの紙保存は2023年末まで猶予措置により容認されていましたが、2024年1月以降は電子データ保存が原則です。現在はPDF請求書等も電子データでの保存が必須ですので注意してください。
紙で受領した請求書の保存方法は大きく分けて2つあります。①紙のまま原本を保管する方法と、②スキャナで読み取って電子データで保管する方法です。それぞれのメリット・注意点を押さえておきましょう。

紙で受け取った請求書は、原本をそのままファイリングして保存すれば問題ありません。経理処理(会計ソフトへの入力や仕訳)が終わった後、タグ付けやファイリングを行い、書類庫に保管してください。法律上は原則として保存することが求められています。コピーや写しで済ませてしまうと、税務調査の際に、改ざんのリスクや不正会計を疑われてしまいます。したがって、必ず正式な原本を保存する必要があります。
会計処理後、請求書に処理済みの印や伝票番号を付け、月ごとや取引先ごとに分類してバインダーに綴じます。バインダーの背表紙やインデックスに年月や得意先名を書いておけば検索も容易です。これらのファイルは社内の書庫やキャビネットなど定められた保存場所に保管します。社内で保存ルールを決めて徹底すれば、後から請求書を探す手間も減り、税務調査の際もスムーズに提示することが可能です。

紙の請求書を電子データ化して保存することも可能です。電子帳簿保存法が定める「スキャナ保存」の要件を満たせば、紙の原本をスキャンしてPDFなどの電子データとして保存できます。スキャナ保存を活用すれば、紙の書類を減らして保管スペースを節約できるほか、データ上で管理することによって検索も容易になり業務効率化につながります。
ただし、スキャナ保存を行うには満たすべき重要な要件があります。主なポイントを以下にまとめます。
書類を受け取ってから最大およそ70日以内に電子化し、電子データに日時の証明(タイムスタンプ)を付与する必要があります。
例えば200dpi以上の解像度、カラー画像(赤・緑・青それぞれ256階調以上)でスキャンし、原本と同等に鮮明に保存します。
電子データのファイル名に「取引年月日」、「取引先」、「取引金額」等を記載することで、迅速かつ容易に必要な電子データを開示できるようにします。
データ改ざん防止措置を確保するために、タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムのほか、事務処理規定を設けて真実性の確保を行います。
現在では事前に税務署の承認を得る必要はなく、自社の判断でいつでもスキャナ保存を導入することが可能です。
要件を満たす専用ソフトやクラウドサービスも市販されていますので、それらを活用すればタイムスタンプ付与や検索機能の確保も比較的容易に実現可能です。スキャナ保存を適切に行えば、紙原本を手元に残さなくても法令に沿った形で請求書を保存することができます。
また2022年以降は、スキャナ保存の際、受領者の自署(署名押印)は不要となっています。
電子データで受領した請求書(メール添付のPDF、Web発行の請求書データなど)は、必ず電子データのまま保存しなければなりません。紙に印刷して紙ファイルで保存する方法は認められていません。
例えば、メールで受け取ったPDF請求書やオンライン上の請求書は、紙に出力せずにそのまま電子データで保存する必要があります。電子データの請求書を保存する場合、データの真実性と可視性を確保することが求められます。
真実性とは保存したデータが改ざん・削除されていないこと、可視性とは保存したデータを検索・表示できる状態にすることを指します。具体的には、先述のスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与や変更履歴の残るシステムでデータの信頼性を担保し、取引日や金額で検索できるように可視性を確保する必要があります。これら詳細な要件については、国税庁の公表するガイドラインやQ&Aを参照してください。
重要なのは、電子取引で受け取った請求書を紙にプリントアウトして保存することは認められていないという点です。仮に社内手続き上、PDFを印刷して回覧・承認を行ったとしても、必ず元の電子ファイルを電子保存しておく必要があります。印刷物のみでは電子帳簿保存法に沿った保存とは認められず、税務調査の際に電子データの提示が求められるため、電子データの請求書は社内のサーバーやクラウド上できちんと管理し、バックアップも備えておく必要があります。

紙・電子を問わず、請求書は税法で定められた期間は保存する義務があります。法人(会社)の場合は原則として7年間、請求書や帳簿を保存しなければなりません。
ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度、または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存義務となります。一方、個人事業主の場合は原則5年間の保存義務があります(所得税法)。
ただし、個人事業主でも青色申告で欠損金の繰越控除を受けている場合は7年間の保存が必要になるほか、近年開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)において課税事業者となって消費税の仕入税額控除を受ける場合は、受領した請求書類を7年間保存することが求められます。
逆に言えば、消費税の納税義務が免除されている免税事業者であれば消費税法上は7年間の保存義務はなく、所得税法における保存期間と同様に5年間の保存が基準となります。しかし、消費税の免税事業者であっても、現金出納帳や仕訳帳、総勘定元帳などの会計帳簿の保存期間は7年間となっているので、実務上は請求書の保存期間も会計帳簿の保存期間と合わせて7年間保存しておくことが一般的です。なお、保存期間の起算日は注意が必要です。法人ではその事業年度の確定申告期限の翌日から起算して7年となります。
個人事業主の場合も、該当年の確定申告期限の翌日から5年(または7年)となります。紙の請求書であっても電子データであっても、保存期間は同様です。 スキャン保存したからといって短くなるわけではなく、法律で定められた期間を保存しておく必要があります。

A.はい、要件を満たしたスキャナ保存を行った後であれば、紙の原本を破棄しても差し支えありません。電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存が適切に行われていれば、法律上も紙原本の保存義務は電子データに置き換えられています。
実際、国税庁も「読み取った後の紙の書類を廃棄できる」ことをメリットの一つとして挙げています。紙を捨てることでファイリング作業の手間や保管スペースを削減できるのは大きな利点です。
ただし、破棄はスキャナ保存の要件を完全に満たした後に限ります。例えば、スキャン画像が不鮮明だったりタイムスタンプ付与を失念したりした場合、後日税務調査で問題になる可能性があります。紙原本を処分する際は、本当に要件をクリアしたデータ保存ができているか最終確認してからにしましょう。
A.いいえ、電子取引で受領した請求書を紙に出力して保存する方法は認められていません。 電子帳簿保存法では、電子データでやり取りした請求書等はデータのまま保存することが義務付けられています。
2024年以降、このルールは原則すべての事業者に適用されており、紙に印刷してファイルしただけでは法律上の保存要件を満たしません。
仮に紙に出力したものを保管しても、それは「国税関係書類の保存」としては扱われず、電子データを保存しなかったことによる違反となり得ます。したがって、電子データで受け取った請求書は必ず電子データのまま保存し、適宜バックアップを取るなどして紛失や消去に備えてください。データ保存に不安がある場合でも、プリントアウトで済ませるのではなく、前述の真実性の確保・可視性の確保の要件を満たす形でデータを保存するようにしましょう。
※紙の請求書は電子化(スキャナ保存)することができる一方、電子データの請求書を紙にすることはできない。つまり「紙→電子はOK、電子→紙はNG」という点を押さえておくと理解しやすいでしょう。

電子帳簿保存法の改正により、請求書の保存方法は取引形態に応じて適切に選択する必要があります。紙で受け取った請求書は紙のまま保存することも可能ですが、スキャナ保存を活用すればペーパーレス化による管理効率の向上が期待できます。
一方、電子取引の請求書データは必ず電子のまま保存することが法律で義務付けられているため、紙に頼った従来のやり方を続けないよう注意が必要です。法令遵守(コンプライアンス)はもちろん重要ですが、単にルールに従うだけでなく業務効率化のチャンスと捉えることもできます。
例えば、電子保存に対応した会計ソフトやドキュメント管理ツールを導入すれば、タイムスタンプの自動付与や検索・管理機能により、日々の経理業務の手間を減らすことができます。結果として、テレワーク環境でもスムーズに経理処理が行えるなど、生産性向上にもつながるでしょう。
監修

税理士 高橋龍二
1957年、山形県尾花沢市生まれ。1982年、税理士試験合格。1987年、税理士登録。2022年、税理士法人伊藤・高橋事務所を開設し、代表社員税理士となる。日本税理士会連合会理事、東北税理士会副会長、東北税理士会山形県支部連合会会長(いずれも2023年7月退任)。多くのクライアントとともに、地方において豊かに暮らしていくことを目指している。